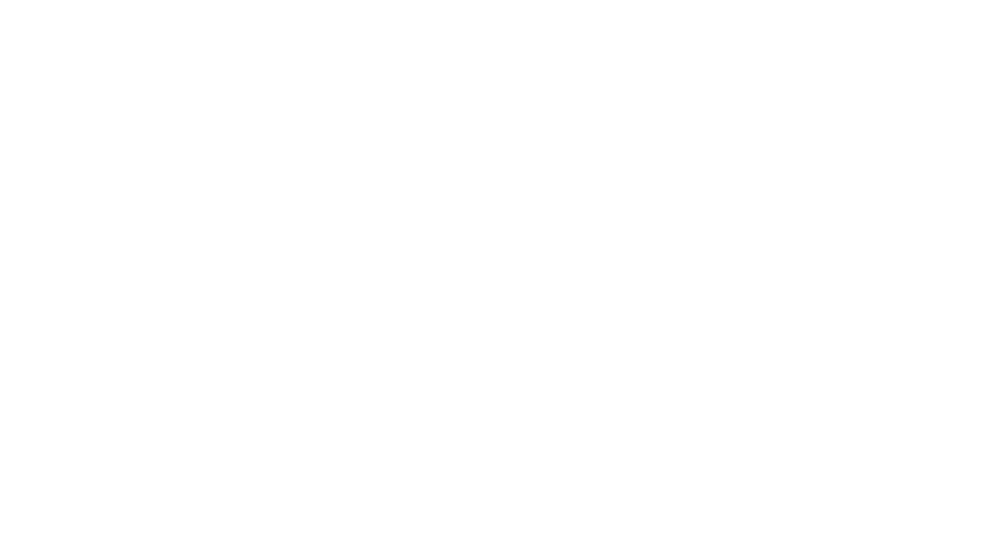/
サーファーは
いつも風を気にしています
\
サーフィン大好きな気象予報士です。
そうなんです
サーファーはいつも風を気にして
いるんですよね
海に行く前日はもとより
平日の満員電車に揺られている
ときですら
お気に入りのサーフポイントの
風と波が気になってしまうんです。
風があるから波がたつ訳で
どこでどんな風が吹いているのかが
わかれば
どこで波が発達して大きくなっているのか
もわかってくることになります。
今回はそんな
「波をつくるための風」
について記事にしていこうと思います
サーファーにとっての風とは

本ブログでは、
毎日の気圧配置の変化によって
主に千葉・湘南エリアの波が
どんなコンディションになるのか
なっていきそうなのかを、
毎日の天気図とアメダスなどのデータを
掲載しながら記事にしています。
毎日の天気図から見られる気圧配置から
波のうねりの向きや強さ、
時間帯による風向きの変化と強さについての
現状と予想を毎日ブログに投稿していってます。
~
毎日更新の記事にも記載しているとおり、
サーファーはいつも波のことを気にしていますが、
同時に風のことも常に気にしています。
波・うねりの向きや強さよりも、
風向きと強さのほうが時間推移による
変化のスピードが速いため、
どちらかというと海に来た段階では、
波よりも風のほうを気にしての
行動になることが多いのではないかと
思います。
~
2つの側面があります。
ひとつは、
波をつくるための風
もうひとつは、
波の形を左右する沿岸で吹く風
です。
今回は、波を知る上で
必ず知っておくべき
”風”について
記載していきますが
ただ一口に風といっても、
1つの記事では到底書ききれない
くらいの内容があります。
~
まずは、風についてのイントロとして、
サーファーが知っておきたい風
のことから書いていきます。
いい波に乗るためには、
波情報だけでなく
こんなことを知っておいたら
いいんじゃないかなという内容です。
”風”はどこで吹くのか

サーフィンは波に乗るスポーツですが、
その波はどうやってつくられるのか??
波が発生するために、
最も重要なのが風になります。
海上で風が吹くから波がたち、
その波が海上を長い距離を伝搬して
ビーチに打ち寄せる訳です。
息を吹くと小さな波ができますよね
海の上でも同じことが発生していて、
その風の吹く規模が大きいから
波が発生すると考えればいいかと思います。![]()
どこで波が発生するのか
を知るためには、
風がどこで吹くか
を知らないといけません。
予想する上で
最も重要なのは、
風がどこで吹いているか
それでは、
風とは何が起因して
発生するのでしょうか?
太陽エネルギーを起因とした
基本的な風の発生メカニズムについては、
いろんなサイトにて
説明が記載されていると思うので、
ここでは詳細は記載しませんが、
その辺を端折って覚えておきたい
ところだけ記載すると、
気圧の低いところに
向かって風は吹く
ということです。
違う表現の仕方をすると、
高気圧から低気圧に
向かって風は吹く
ということですね。
つまり、
天気図を見れば
高気圧と低気圧が書いてあるから、
どこで風が吹いているのか
がわかるということです。
波をつくるための風とは

天気図を見れば、
どの辺に風が吹いているのかがわかる、
ということがわかりました。
それでは、
どういう条件のときに
波が大きくなるのでしょうか?
~
風が強く吹いている海上で
波は大きくなる
ということは
直感的にわかるかと思いますが、
二つの要素があります
- 吹走距離
風が吹いている距離が長いほど、波は大きくなる - 吹続時間
風が吹いている時間が長いほど、波は大きくなる
つまり、
長い時間・長い距離を吹くと、
波は大きくなる
ということです。
風が強いところだけわかっても不十分で、
その風がどれだけの距離、
どれだけの時間吹いていたかで
波の発達度合いが異なってくる
ということです。
これを知るには・・・、
気圧配置の推移・流れを見ていると、
だんだんわかってきます
その日のある時刻の天気図で
気圧配置を見れば、
波の発達するエリアがどこなのかが
何となくわかります。
しかし、
ある時刻の天気図だけでは、
どれくらい長い時間・長い距離を
風が吹いているのかがわからない
部分があります
これまでの気圧配置の推移を
見ることで、
波がどこで発達するのかが
だんだんと見えるようになってきます。
どこで風が強く吹くのか
風は気圧の高いところから
低いところに向けて吹く
ということがわかりました。
等圧線の間隔が狭いところが
風が強く吹くところ
ということは、
容易に想像できるかと思います。
高気圧を山、低気圧を谷として
考えてみれば、
この間の等圧線の間隔が狭いほど
急な傾斜になるのは
イメージがつきやすいですよね。
急な傾斜になっているということは、
より風が強く吹く場所
ということになります。
~
台風の等圧線を見てみると、
中心から同心円状に等圧線が
何本も狭い間隔で記載されています。
ということは、
それだけ中心付近の気圧が
周囲と比較して低くなっている
ということなので、
傾斜も大きく
強い風が台風中心に向けて
吹き込んでいるということになります。
~
また風が吹くのは
低気圧に向けての風ばかりという訳ではなく、
高気圧の中心から外に向けて
吹きだされる風も
波の発達には欠かせないものです。
高気圧からの吹き出しサーファーは海に行く前に必ず波の状況がどうなのかを確認します。今のこの時代は波情報やSNSが発達していて、海にいかなくても波のコンディションやブレイクの様子が写真や動画で見れるようになりましたが、波予想の基本は天[…]
低気圧と高気圧のそれぞれの風の吹き方、
その吹き方に大きな影響を及ぼす
”コリオリの力”については、
また別の記事にて詳しく記載していこうと思います。
はるべえはるべえ@波乗りお天気ブログを毎日更新している気象予報士です/貴重な週末の休みの日に海に行くならいい波に乗りたいですよね!\週末サーファーの方なら誰もがそう思っているかと思いま[…]
どこで長い距離・長い時間 風は吹くのか
これは前述したように、
天気図の推移・流れを
ある程度把握しておかないといけない
のですが、
「慣れ」が必要な部分がありますので
とりあえず・・・
波は発達して大きな波になる
ということだけ、
まずはざっくりわかってもらえれば
よいと思います。
海に行く前に
じっくり天気図の気圧配置の推移を
見ている時間もないことが多いので、
なんとなくこの向きの波が発達してそうだな、
くらいで見ておけばいいと思います。
~
ある地点に対する
波を考える場合には、
- その地点に向かう波が
発生する海域(風場)が
どこにあるのか? - その風場が
どれくらいの大きさで
どれくらい長い時間
あるのか?
を天気図から見つけます。
なぜサーファーが台風に注目するのか?[caption id="attachment_8459" align="alignleft" width="2016"] 某ポイント:台風の強い南うねりが入ったときに素晴らしい波が現れる[/capt[…]
~
例えば以下の地上天気図上で、
千葉に向かって風が吹いている
海域はどこなのか?

上記は2018年8月18日午前3時
の地上天気図。
- 台風19号が日本の南にあり、
本州は移動性の高気圧に覆われている。 - 北海道の東には低気圧があって、
そこから寒冷前線が南にのびている。 - はるか東の海上には
太平洋高気圧が停滞している
といった感じの夏の天気図です。
~
この場合だと、
千葉に向けて風が吹いているのは、
主に以下3つの風場となります。
- 台風18号の右半円にある
南向きの風場 - 北海道の東の低気圧からの
北~北東の風場 - 太平洋高気圧からの
東から南東の風場
この3つの風場それぞれにおいて
チェックすべき点は、
- どれくらい強い風が
吹いているのか?(等圧線の間隔) - 千葉にむけてどれくらいの長さで
吹いているのか?(風場の長さ) - 過去何日かの気圧配置を見て、
千葉に向けてどれくらいの時間
この風場が継続しているのか?
これらがわかると、
どの方向からのうねりが
反応しているのかが、
”なんとなくざっくり”
わかるようになります。
実際この2018年8月18日は、
北海道の東の低気圧からの北東うねりと
東海上の太平洋高気圧からの東うねりが
まざった波が反応し、一宮で腹胸くらいのサイズ。
台風からの南うねりは
前線によりややブロックされた感じで、
次の日の19日朝一には
千葉と湘南に南東うねりが
ヒットしはじめました。
8/18 3:00 ASAS 気圧配置と波情報日本海に中心を持つ高気圧に覆われ今朝も涼しい朝を迎えた。8月としての最低気温を更新した地点もあるようであり湿度も低く秋を感じられる陽気に。台風19号は北緯24度東経140度付近にあり、北北[…]
8/19 3:00 ASAS 気圧配置と波情報~台風19号は昨日とほぼ同じ位置に停滞気味。北緯25度東経140度付近にあり、西北西にゆっくり移動。同心円状に等圧線を描いており衛星画像ではまさに台風という姿で眼もはっきりとしている。今夜9時[…]
![]()
こんな感じの観点で
地上天気図を見てみると、
どの方向からの波が
来ているのか?
なんとなくわかります。
実際はこれら風場の風の強さと
吹く長さと吹いている時間を元にして
ある計算式にあてはめると、
ざっくりどれくらいの波高なのかを
求めることはできます。
ただサーファーが乗る波の高さが
求められる訳ではないので、
あくまで参考の値になりますが
計算で求めることも可能ということです。
~
実際はそんなことやっている
時間ないので、
天気図だけみて
ざっくりこんな内容がわかれば、
更に楽しくなる!
のではないでしょうか。
~
今回は、“波をつくるための風”
について記載してみました。
まずは風についての
イントロダクション的な感じで記載してみましたが
基本的なところなので
多くは知っている内容だったかもしれません
改めて「波をつくる風」について
少しでも意識してもらえればと思います。
~
次回は、
もう1つの風である
”波の形を左右する沿岸で吹く風“
について記載していきます。
~
kindle電子書籍: いい波にのるために
本記事の内容は
こちらのKindle電子書籍にて
内容一部追記・更新して出版しています。

「Kindle Unlimited」への登録で、
こちらの本は30日間無料で読めます。
Amazonユーザなら登録は簡単です
Kindle Unlimitedはこちらから
Kindle Unlimitedについて
詳しくはこちらの記事もご覧ください。
【特典あり】『Kindle Unlimited』サーフィンライフなど本や雑誌が読み放題!
https://asasfsas24.com/20220619/wave-27228/
※「はるべえ特典」として有料noteをプレゼントしてます